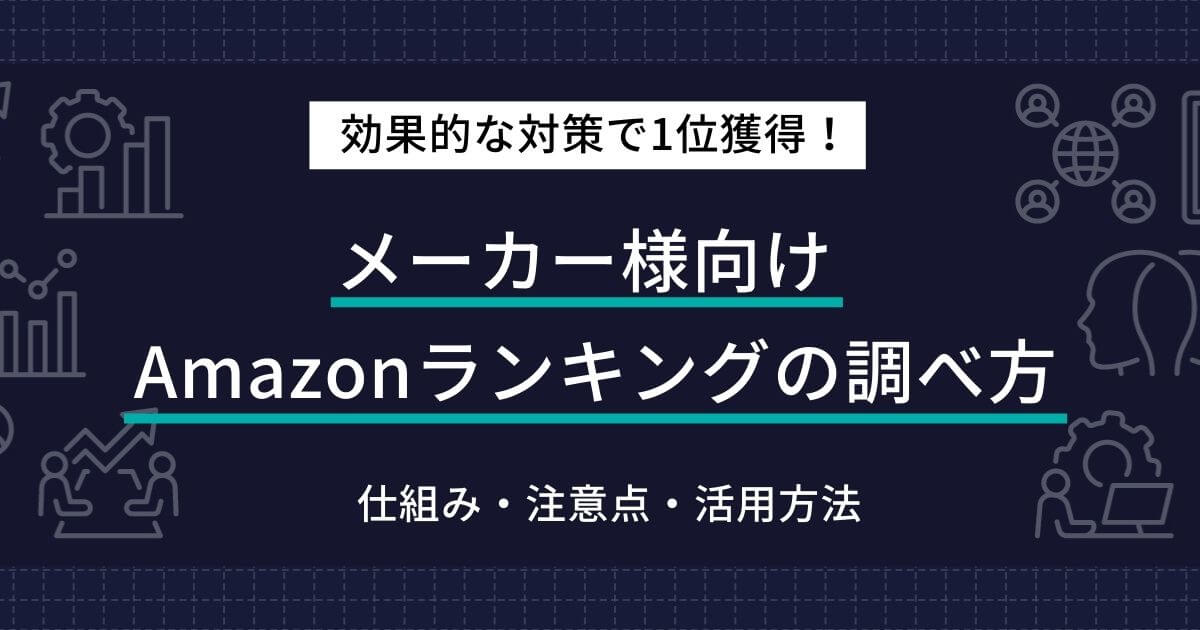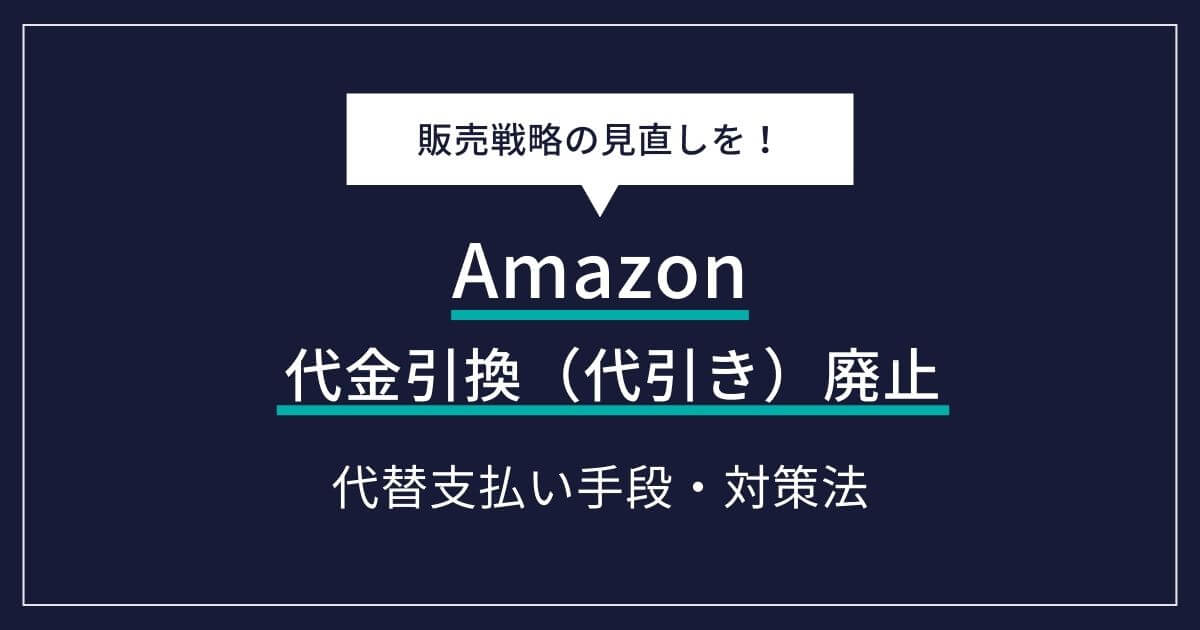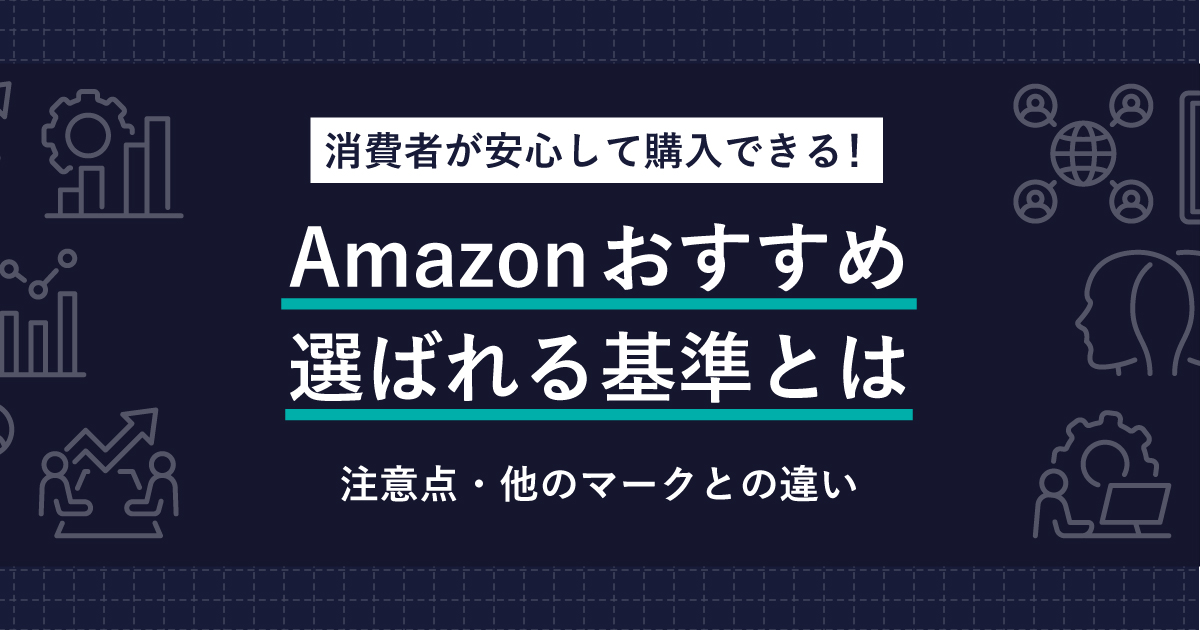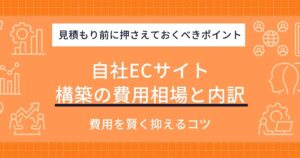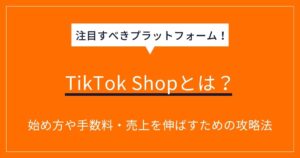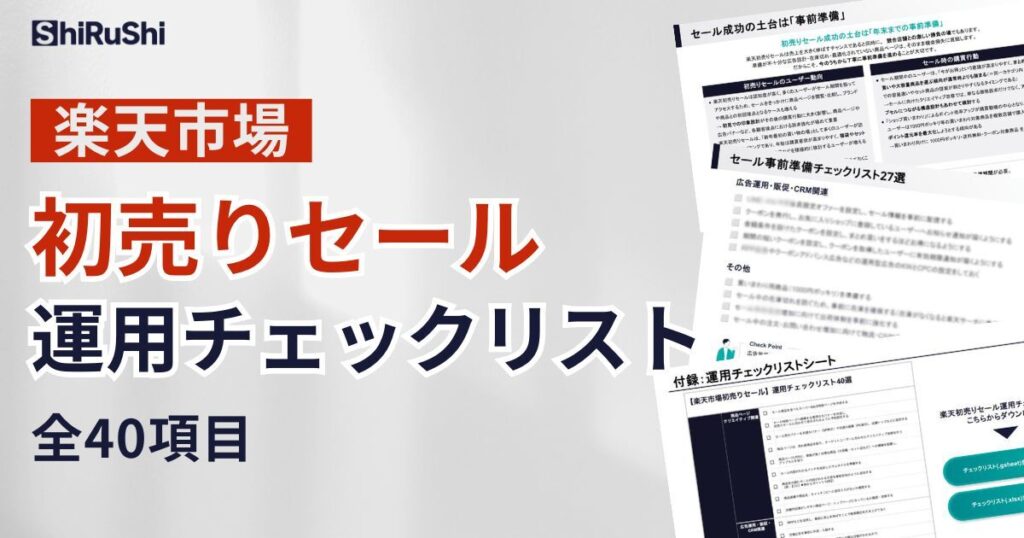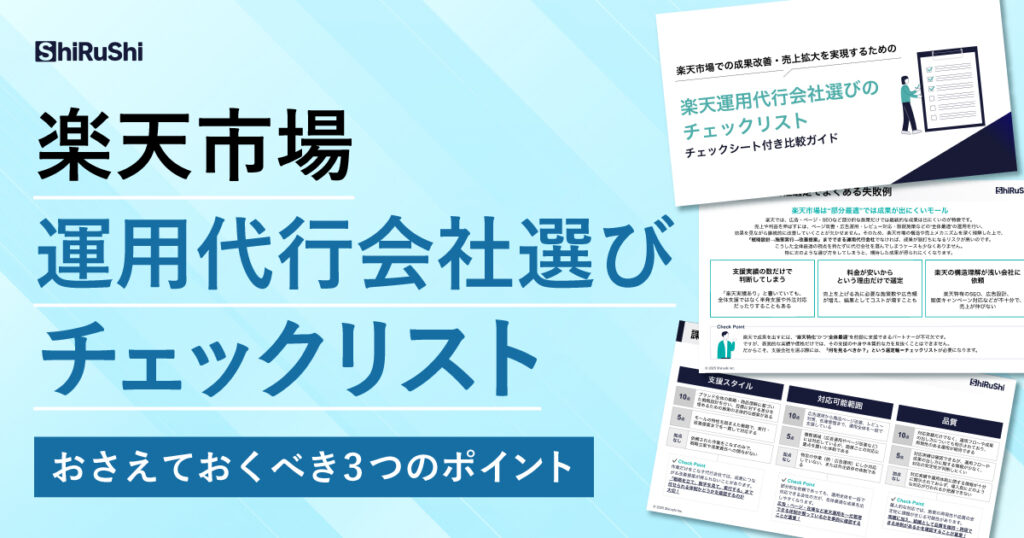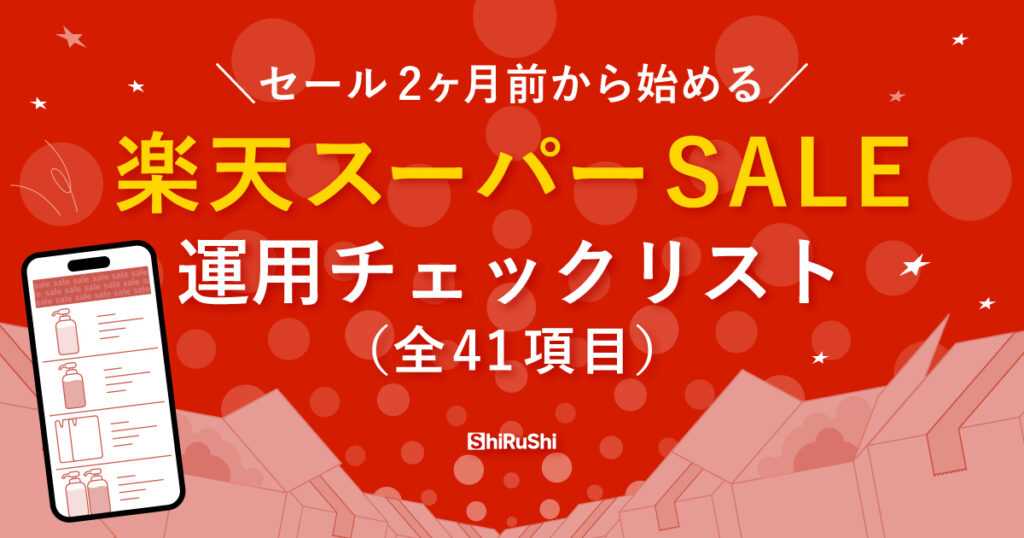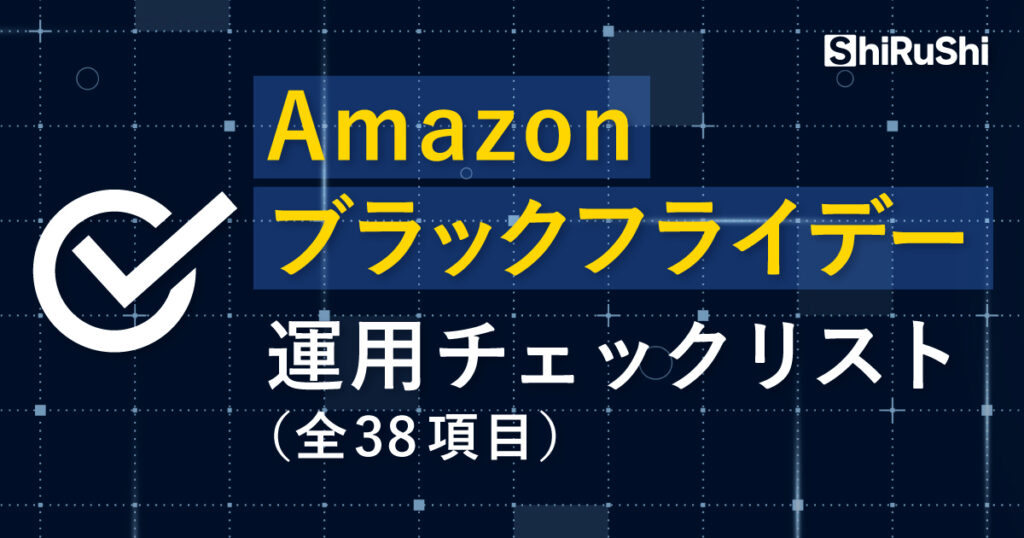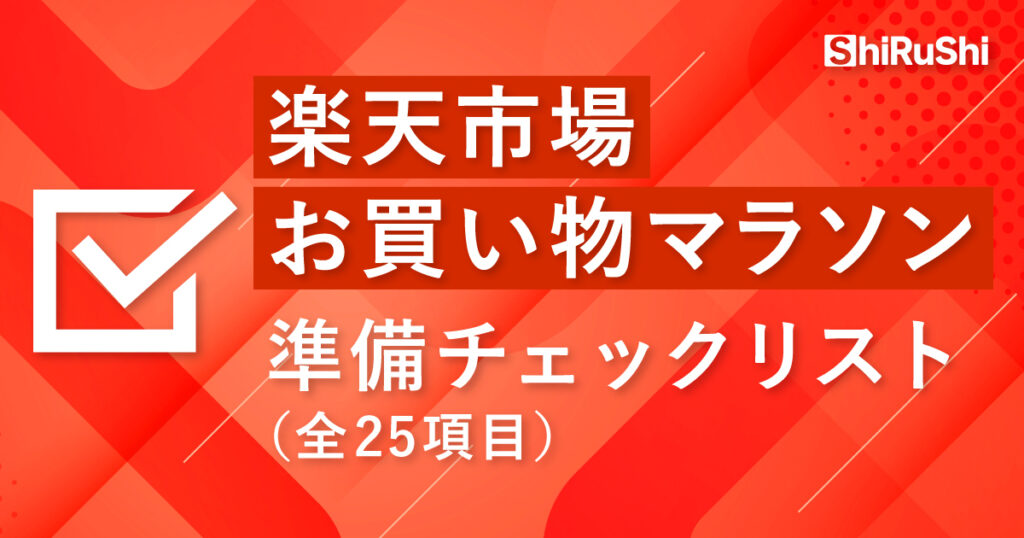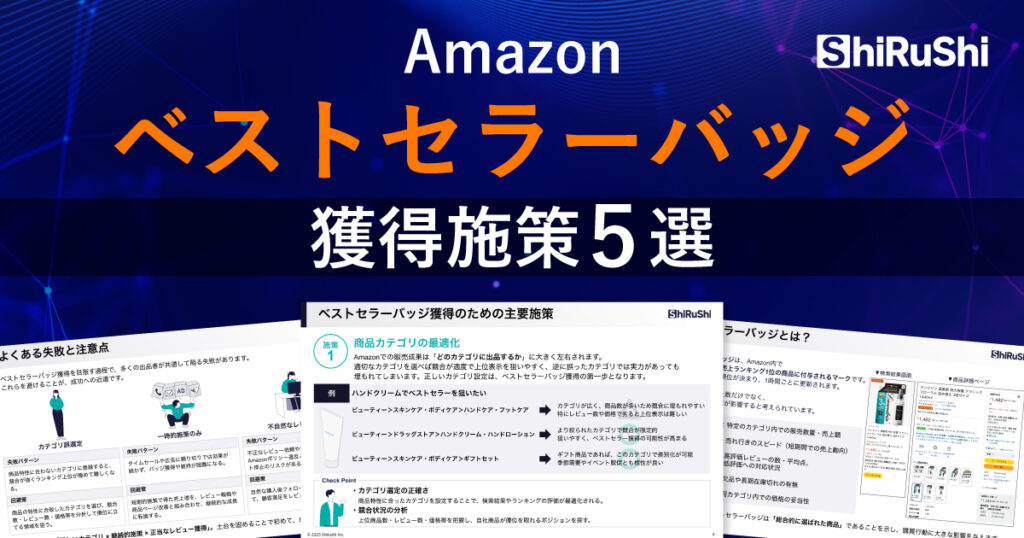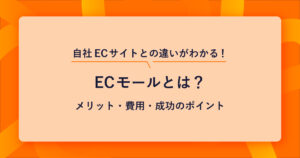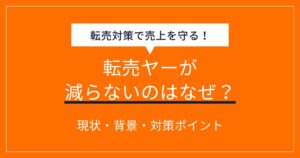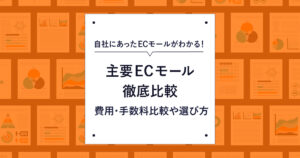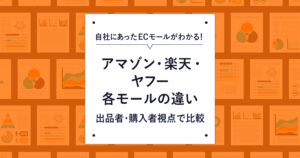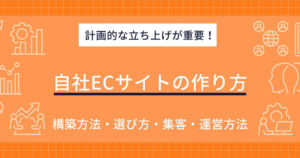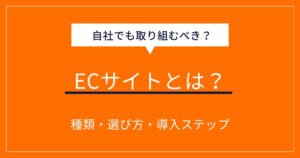自社ECサイトのメリット・デメリットを徹底解説【メーカー・ブランドオーナー必見】
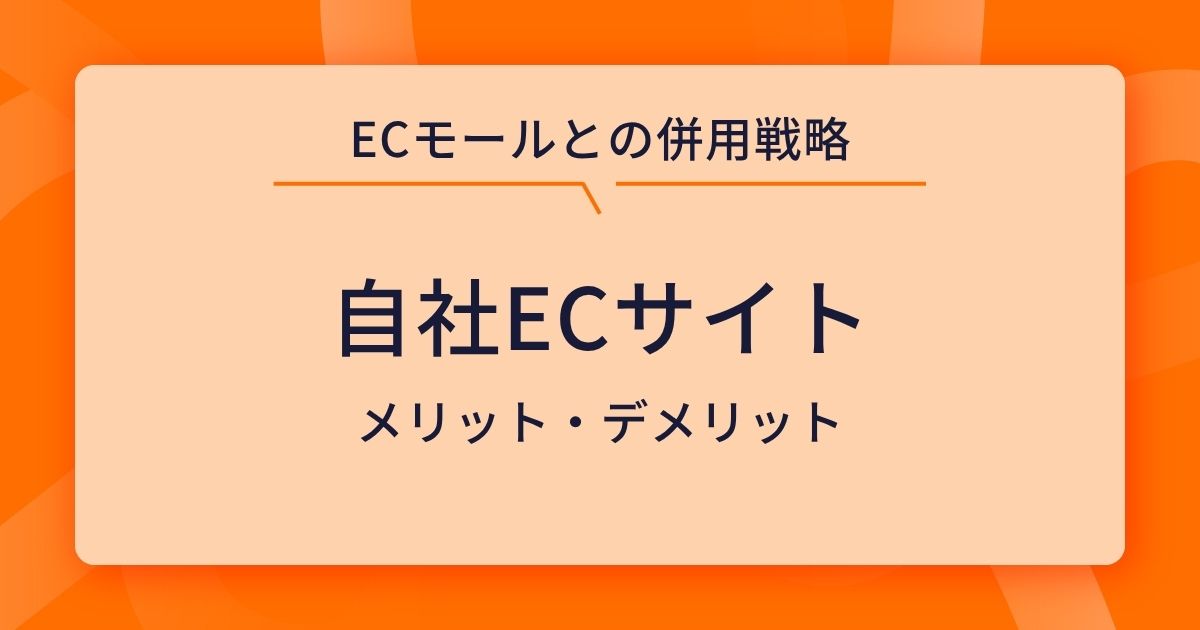
ECサイトの運営において、ECモールへの出店は集客面で大きな魅力がありますが、手数料の負担やブランディングの制約といった課題も少なくありません。
この記事では、ECモールに出店中のメーカーやブランドオーナー様に向けて、自社ECサイトを持つことの具体的なメリットと、知っておくべきデメリット(注意点)を徹底解説します。
ECモールだけで本当に大丈夫?自社ECサイトがもたらす可能性とは
ECモールへの出店は、多くのメーカー様やブランドオーナー様にとって、オンライン販売を始めるための一般的な選択肢のひとつです。
確かに、楽天市場やAmazonといった大手ECモールは、圧倒的な集客力を持ち、出店すれば一定のアクセスが見込めるという大きなメリットがあります。
しかし、運営を続けるなかで、
- 「思ったよりも手数料が高く、利益が圧迫されている…」
- 「モール内での価格競争が激しく、ブランド価値を維持しにくい…」
- 「顧客情報が手に入らず、リピート施策が打ちにくい…」
- 「モールの規約やデザインの制約で、独自のブランドイメージを伝えきれない…」
といった悩みや課題を感じている方も多いのではないでしょうか?もし、これらの課題に心当たりがあるなら、「自社ECサイト」という選択肢を検討する価値が大いにあります。
自社ECサイトとは、文字通り自社で独自に構築・運営するオンラインショップのことです。
ECモールという「ショッピングセンターのテナント」ではなく、「自社の路面店」を持つイメージに近いかもしれません。
自社ECサイトを持つことで、ECモールでは実現しにくかったブランドの世界観の自由な表現、顧客とのダイレクトなコミュニケーション、そして何よりも手数料に縛られない収益構造の確立など、多くの可能性が広がります。
もちろん、集客や運営に手間がかかる側面もありますが、それを補って余りあるメリットが期待できます。
ECモールとは違う!自社ECサイトならではの8つの主なメリット
自社ECサイトには、ECモール出店では得られない多くのメリットが存在します。
手数料削減による利益率向上、自由なブランディング、顧客データの活用、顧客との直接的な関係構築、独自のマーケティング展開、運営の安定性、LTV向上、柔軟なテストマーケティングなどが挙げられます。
これらのメリットを理解することで、自社ECサイトの価値が見えてくるはずです。
ECモールでの販売も有効な手段ですが、自社ECサイトには、それを上回る独自の魅力がたくさん詰まっています。
ここでは、メーカー様やブランドオーナー様にとって特に重要な8つのメリットを、ECモールと比較しながら具体的に見ていきましょう。
EC運用の不安は無料相談で解消。専門家に話してスムーズな改善を目指しましょう
⇒まずは無料相談する
【メリット1】手数料からの解放と価格決定権による利益率アップ
ECモールに出店していると、どうしても避けられないのが販売手数料やシステム利用料です。
売上が上がるほど、この手数料の負担は大きくなり、「頑張って売ったのに、手元に残る利益が少ない…」と感じることもあるのではないでしょうか。
自社ECサイトの最大のメリットのひとつが、この手数料負担を大幅に軽減できる点です。
- 販売手数料が原則かからない: ASPカートなどを利用する場合でも、月額固定費や決済手数料はかかりますが、売上に応じた販売手数料はECモールに比べて格段に低いか、かからないケースがほとんどです。
- 価格決定権を自社で持てる: ECモール内では、他社との価格競争に巻き込まれやすく、不本意な値下げを強いられることもあります。しかし、自社ECサイトであれば、ブランド価値に見合った適正価格で商品を販売できます。
例えば、ECモールで月商300万円、販売手数料が10%だとすると、30万円が手数料として引かれます。
自社ECサイトで同じ売上を達成できれば、この30万円がそのまま利益に上乗せされる可能性があるのです。これは、利益率の大幅な改善に直結します。
【メリット2】ブランドの世界観を自由に表現できるデザインとコンテンツ
ECモールでは、提供されるデザインテンプレートの範囲内でしかサイトを構築できず、どのショップも似たような見た目になりがちです。
これでは、せっかくのブランドの個性やストーリーを十分に伝えることが難しいですよね。
自社ECサイトなら、デザインの自由度が格段に高まります。
- オリジナルのサイトデザイン: ブランドカラー、フォント、レイアウトなど、細部に至るまでこだわりを反映し、ブランドの世界観を視覚的に表現できます。
- 豊富なコンテンツ展開: 商品紹介ページだけでなく、ブランドヒストリー、製造工程のこだわり、お客様の声、スタッフブログなど、多様なコンテンツを通じてブランドの魅力を多角的に発信できます。
具体的には、高品質な商品画像や動画をふんだんに使用したり、ブランドのコンセプトを伝える特集ページを作成したりと、ECモールでは難しかったクリエイティブな表現が可能になります。
これにより、顧客は商品だけでなく、ブランドそのものに愛着を感じやすくなります。
【メリット3】顧客データを直接収集・分析し、CRM施策へ活用
ECモールで商品を販売していると、「どんなお客様が買ってくれているのか」「リピートしてくれているのか」といった詳細な顧客情報が手に入りにくいという課題があります。
顧客データはECモール側が管理しているため、自社で自由に活用することが難しいのが現状です。
自社ECサイトでは、購入履歴、会員情報、サイト内での行動履歴といった貴重な顧客データを自社で直接収集・蓄積できます。
これが何を意味するかというと、効果的なCRM(顧客関係管理)施策を展開できるようになるということです。
- 顧客分析: 収集したデータを分析し、優良顧客の特定、顧客セグメントの作成などが可能になります。
- パーソナライズされたアプローチ: 顧客の購買傾向や興味関心に合わせて、おすすめ商品を表示したり、特別なキャンペーン情報をお知らせしたりと、一人ひとりに最適化されたコミュニケーションが実現できます。
- リピート購入の促進: 購入後のフォローアップメールや、誕生日クーポンの発行など、顧客との継続的な関係を築き、リピート購入を促す施策を打つことができます。
例えば、「過去にAという商品を購入した顧客に、関連商品Bの割引クーポンを送る」といった具体的な施策が、データに基づいて実施できるようになります。
【メリット4】顧客と直接繋がり、ファン化・ロイヤルカスタマー育成を実現
ECモールを介した販売では、顧客とのコミュニケーションが限定的になりがちです。お問い合わせ対応はあっても、それ以上の深い関係性を築くのは難しいかもしれません。
自社ECサイトは、顧客と直接的かつ継続的なコミュニケーションを取るためのプラットフォームとなります。
- 多様なコミュニケーションチャネル: メルマガ配信、お問い合わせフォーム、チャットサポート、商品レビューへの返信、SNS連携などを通じて、顧客と双方向のやり取りが可能です。
- 顧客の声の収集: 顧客からの意見や要望を直接受け止め、商品開発やサービス改善に活かすことができます。
- コミュニティ形成: ブランドの世界観に共感する顧客同士が交流できる場を提供することも可能です。
こうした直接的なコミュニケーションを通じて、顧客はブランドに対して親近感や信頼感を抱きやすくなります。
その結果、単なる購入者から熱心なファンへ、そして長期的にブランドを支えてくれるロイヤルカスタマーへと育成していくことが期待できます。
【メリット5】SEOからSNSまで、独自のマーケティング戦略を幅広く展開
ECモール内の集客は、基本的にモール内SEOやモールが提供する広告枠に依存する形になります。そのため、独自のマーケティング戦略を自由に展開するには限界があります。
自社ECサイトであれば、SEO(検索エンジン最適化)、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、リスティング広告、アフィリエイト広告など、多種多様なマーケティング施策を自社の戦略に基づいて自由に組み合わせ、実行できます。
- SEO対策: ターゲット顧客が検索するキーワードで自社サイトが上位表示されるように対策することで、広告費をかけずに継続的な集客が見込めます。
- コンテンツマーケティング: 役立つ情報やブランドストーリーを発信するブログ記事やコラムを作成し、潜在顧客層へのアプローチやブランド理解の深化を図れます。
- SNS連携: InstagramやX(旧Twitter)などのSNSアカウントと連携し、新商品情報やキャンペーン情報を拡散したり、ユーザーとのエンゲージメントを高めたりできます。
例えば、「オーガニックコスメ 敏感肌」といったキーワードで検索するユーザーに対し、自社ECサイトのブログ記事で有益な情報を提供し、自然な形で商品購入へ誘導するといった戦略が可能です。
【メリット6】モールの規約変更に左右されない、安定した事業運営
ECモールに出店していると、モールの規約変更、手数料の改定、システム仕様の変更といった外部要因に、自社のEC戦略が大きく影響を受けることがあります。
ときには、予期せぬタイミングで大きな変更があり、対応に追われるケースも少なくありません。
自社ECサイトは、いわば「自社のお店」です。そのため、プラットフォーム側の都合に振り回されることなく、自社のペースで安定した事業運営が可能になります。
- 規約変更のリスク回避: モールの規約に縛られることなく、自社の販売方針や顧客対応ポリシーを貫けます。
- 手数料変動リスクの低減: モール側の一方的な手数料改定によって、突然利益構造が悪化するといったリスクを避けられます。
- 長期的な視点での戦略立案: 外部環境の変化に一喜一憂することなく、腰を据えて長期的なブランド戦略や販売戦略を計画・実行できます。
もちろん、法改正など社会全体のルール変更には対応する必要がありますが、特定のプラットフォームの意向に左右されないという点は、事業の安定性において非常に大きなメリットと言えるでしょう。
【メリット7】長期的な視点でLTV(顧客生涯価値)を最大化
ECモールでは、どうしても「いかに多くの新規顧客を獲得するか」「いかに今月の売上目標を達成するか」といった短期的な視点での施策が中心になりがちです。
その結果、LTV(顧客生涯価値)、つまり一人の顧客が取引期間全体を通じて自社にもたらしてくれる総利益、という視点が薄れてしまうことがあります。
自社ECサイトでは、メリット3で述べた顧客データの活用や、メリット4で述べた顧客との直接的な関係構築を通じて、LTVの最大化を目指した取り組みがしやすくなります。
- リピート購入の促進: 既存顧客に対して、適切なタイミングで適切な情報を提供し、継続的な購入を促します。
- アップセル・クロスセル: 顧客の購買履歴や好みに合わせて、より高単価な商品(アップセル)や関連商品(クロスセル)を提案します。
- ブランドロイヤルティの向上: 顧客満足度を高め、ブランドへの愛着を深めることで、長期的なファンになってもらいます。
例えば、初回購入者には感謝のメッセージと共に次回使えるクーポンを送り、その後も定期的に新商品情報やお得なキャンペーン情報を配信することで、顧客との関係を維持し、LTVを高めていくことができます。
【メリット8】新商品や限定企画など、柔軟なテストマーケティングが可能
新商品を開発した際や、新しい販売戦略を試したい場合、ECモールではその実施に際してモールのルールやシステム上の制約を受けることがあります。
また、大々的に展開する前に、小規模で顧客の反応を見たいというニーズもあるでしょう。
自社ECサイトであれば、新商品の先行販売、数量限定の特別オファー、会員限定のシークレットセールなど、さまざまなテストマーケティングを自社の裁量で柔軟かつ迅速に実施できます。
- 小ロットでのテスト販売: 本格的な量産前に、一部の顧客に向けて新商品をテスト販売し、フィードバックを収集できます。
- 効果測定の容易さ: キャンペーンの反応や売上データを直接分析できるため、施策の効果測定が容易です。
- スピーディーな改善: テスト結果に基づいて、商品やプロモーション方法を迅速に改善し、本格展開に活かすことができます。
例えば、開発中の新商品のプロトタイプを、メルマガ会員限定でモニター販売し、アンケートを実施して意見を募る、といったことが自社ECサイトなら手軽に行えます。
これにより、市場投入後の失敗リスクを低減し、より顧客ニーズに合った商品・サービスを提供できるようになります。
EC運用で悩むならまず無料相談。丁寧なサポートで次の一歩を踏み出しましょう
⇒まずは無料相談する
自社ECサイトのメリットを最大限に活かすための注意点(デメリット)
自社ECサイトは多くのメリットがある一方で、集客を自力で行う必要があり、SEO対策や広告運用が不可欠です。
また、サイト構築や日々の運営には初期費用やランニングコスト、専門知識が求められる場合もあります。これらの注意点を理解し、対策を講じることが成功のカギとなります。
ここまで自社ECサイトの輝かしいメリットをお伝えしてきましたが、もちろん良いことばかりではありません。
メリットを最大限に享受するためには、いくつかの注意点、言い換えればデメリットもしっかりと理解しておく必要があります。
集客は自力で!SEO対策や広告運用など能動的な取り組みが必須
ECモールに出店する最大のメリットのひとつは、モール自体が持つ集客力ですよね。何もしなくても、ある程度のアクセスが見込めるのは大きな魅力です。
しかし、自社ECサイトの場合、この「何もしなくても」というわけにはいきません。
サイトを立ち上げただけでは、大海原にぽつんと浮かぶ小舟のようなもので、誰にも気づいてもらえない可能性があります。つまり、集客は基本的にすべて自力で行う必要があるのです。
具体的には、以下のような能動的な取り組みが不可欠になります。
- SEO(検索エンジン最適化)
Googleなどの検索エンジンで、自社の商品やブランドに関連するキーワードで検索された際に、サイトが上位に表示されるように対策します。これには専門的な知識と継続的な努力が必要です。
- Web広告の運用
リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など、費用をかけてターゲット顧客にサイトを認知してもらうための広告活動です。効果的な運用にはノウハウが求められます。
- コンテンツマーケティング
ターゲット顧客にとって価値のある情報(ブログ記事、動画、お役立ち情報など)を発信し、見込み客を引き寄せ、ファンを育成します。
- SNS運用
Instagram、X(旧Twitter)、FacebookなどのSNSアカウントを運用し、ブランドの認知度向上や顧客とのコミュニケーションを図ります。
これらの集客施策には、時間、労力、そして場合によっては専門知識や広告予算が必要になります。「サイトを作れば売れる」という甘い考えは禁物です。
サイト構築・運営にはコストと専門知識が必要になる場合も
自社ECサイトを立ち上げ、運営していくためには、当然ながらコストがかかります。また、ある程度の専門知識も求められます。
コスト面では、主に以下のようなものがあります。
初期費用
- サイトデザイン費、コーディング費(オリジナルデザインの場合)
- ECカートシステムの導入費用(ASPカート、オープンソース、フルスクラッチなど選択肢により大きく変動)
- 商品撮影費、コンテンツ作成費
運営費用(ランニングコスト)
- サーバーレンタル費、ドメイン維持費
- ECカートシステムの月額利用料
- 決済手数料(クレジットカード決済などを導入する場合)
- サイトの保守・メンテナンス費用
- 広告宣伝費(前述の集客施策にかかる費用)
これらの費用は、どのようなECサイトを構築し、どの程度の規模で運営するかによって大きく異なります。
無料のASPカートから始められるものもあれば、数百万円以上の開発費用がかかる大規模なサイトもあります。
専門知識・スキル面では、以下のようなものが挙げられます。
- Webサイト制作・デザインの知識: 魅力的なサイトを作るための基本的な知識。
- ECサイト運営スキル: 商品登録、在庫管理、受注処理、顧客対応、データ分析など。
- マーケティング知識: SEO、広告運用、SNS活用など、集客に関する知識。
- セキュリティ知識: 顧客の個人情報や決済情報を安全に管理するための知識。
もちろん、これらのすべてを自社でまかなう必要はなく、制作会社やコンサルタントに外部委託するという選択肢もあります。しかし、その場合は当然ながら追加のコストが発生します。
ECモールと自社ECサイトの主な違いを比較表にまとめましたので、参考にしてください。
| 項目 | ECモール出店 | 自社ECサイト構築・運営 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 比較的低い(プランによる) | 構築方法により変動(数万円~数百万円以上) |
| 月額固定費 | プラン料金、システム利用料など | カートシステム利用料、サーバー代、ドメイン代など |
| 販売手数料 | 発生する(売上の数%~十数%) | 原則発生しない(決済手数料は別途) |
| 集客 | モールの集客力に期待できる | 自力での集客が必須 |
| デザイン自由度 | 制限あり | 高い |
| 顧客データ | 限定的 | 自社で保有・活用可能 |
| 運営の自由度 | モールの規約に準拠 | 高い |
これらの注意点を踏まえた上で、自社ECサイトへの挑戦を検討することが重要です。
EC運用の課題は無料相談でクリアに。まずはお気軽にお問い合わせください
⇒まずは無料相談する
特に自社ECサイトがおすすめなメーカー・ブランドの特徴
自社ECサイトは、独自の世界観を大切にするブランド、顧客との長期的な関係構築を目指す企業、ニッチな商品や高付加価値商材で差別化を図りたいメーカー、そして既に一定のファン層を持つ企業に特におすすめです。
これらの特徴に当てはまる場合、自社ECサイトのメリットを最大限に活かせる可能性が高いでしょう。
自社ECサイトは、すべてのメーカー様やブランドオーナー様にとって万能な解決策というわけではありません。
しかし、特定の目的や特徴を持つ企業にとっては、ECモールよりもはるかに大きなメリットをもたらす可能性があります。
ここでは、特に自社ECサイトの導入がおすすめなケースを4つのタイプに分けてご紹介します。
独自の世界観やストーリーを大切にしたいブランド
商品の機能や価格だけでなく、
- ブランドが持つ独自のストーリー
- 創業者の想い
- 製品へのこだわり
- デザインコンセプト
といった「世界観」を顧客に伝えたいと考えているブランドにとって、自社ECサイトは最適な表現の場となります。
- ECモールでは表現しきれないブランドイメージ: ECモールの画一的なデザインや情報量の制約の中では、ブランドの細やかなニュアンスや深いメッセージを伝えるのは困難です。
- 自社ECサイトなら自由な表現が可能: オリジナルのデザイン、豊富なコンテンツ(ブログ、動画、特集ページなど)を通じて、ブランドの世界観を余すところなく表現し、顧客に共感を促すことができます。
例えば、伝統工芸品を扱うメーカー様が、職人の技や歴史的背景を美しい写真や動画と共に紹介したり、オーガニックコスメブランドが、成分へのこだわりや環境への配慮を丁寧に説明したりするのに、自社ECサイトは非常に有効です。
ブランドの付加価値を高め、価格競争に陥らないためにも重要です。
顧客と長期的な関係を築き、リピーターを増やしたい企業
一度商品を購入してくれた顧客と、その後も継続的な関係を築き、LTV(顧客生涯価値)を高めていきたいと考えている企業にとって、自社ECサイトは強力なツールとなります。
- ECモールでは顧客接点が限定的: 購入後のフォローアップや、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションは難しいのが現状です。
- 自社ECサイトならダイレクトな関係構築が可能: 収集した顧客データを活用し、メルマガ配信、パーソナライズされた情報提供、会員限定サービスなどを通じて、顧客との絆を深めることができます。
化粧品や健康食品のようにリピート購入が期待できる商材を扱う企業様が、顧客の肌質や悩みに合わせた情報を提供したり、定期購入者向けの特典を用意したりすることで、顧客満足度を高め、安定したリピーターを獲得することに繋がります。
ニッチな商品や高付加価値な商材で差別化を図りたいメーカー
多くの商品が溢れるECモールでは、どうしても価格競争に巻き込まれやすくなります。
しかし、専門性の高いニッチな商品や、高品質・高価格帯の付加価値の高い商材を扱っているメーカー様であれば、自社ECサイトでその魅力を深く伝えることで、独自のポジションを築くことができます。
- ECモールでは商品の魅力が伝わりにくい: 限られた情報スペースでは、商品の細かな特徴やこだわり、専門的な知識を十分に説明しきれません。
- 自社ECサイトなら専門性をアピール可能: 詳細な商品説明、専門家による解説、活用事例の紹介など、ターゲット顧客が求める情報を深く掘り下げて提供することで、商品の価値を正しく理解してもらい、購買意欲を高めることができます。
例えば、特定の趣味に特化した専門機材を扱うメーカー様や、オーダーメイドの製品を提供するブランド様などが、自社ECサイトでその専門性や独自性を前面に打ち出すことで、熱心なファンを獲得し、高い利益率を確保することが期待できます。
既に一定のファン層やブランド認知度がある企業
実店舗での販売実績がある、SNSで多くのフォロワーがいる、メディア掲載歴があるなど、既にオフラインや他のチャネルである程度のファン層やブランド認知度を獲得している企業にとって、自社ECサイトは新たな顧客接点として非常に有効です。
- 既存顧客の受け皿として機能: ブランドのファンが、より深くブランドの世界観に触れ、安心して商品を購入できる場所を提供できます。
- 集客のハードルが比較的低い: 既存のファンや認知度を活かして、自社ECサイトへスムーズに誘導できるため、ゼロから集客を始める場合に比べて有利です。SNSや実店舗から自社ECサイトへの導線を作ることで、効果的にアクセスを集められます。
人気のインフルエンサーが立ち上げたアパレルブランドや、地域で長年愛されてきた老舗のお菓子屋さんが自社ECサイトを始める場合、既存のファンが初期の顧客となり、口コミを通じてさらに認知が広がる可能性があります。
ECモールへの手数料を支払うことなく、既存ファンからの売上を最大化できます。
上記に挙げた特徴にひとつでも当てはまるようでしたら、自社ECサイトの導入を具体的に検討してみる価値は十分にあると言えるでしょう。
EC運用のプロによる無料相談受付中!お悩み解決の第一歩を踏み出そう
⇒まずは無料相談する
自社ECサイトのメリットを理解し次の一歩を踏み出そう
自社ECサイトは、手数料削減による利益率向上、自由なブランディング、顧客データの活用といった多くのメリットがある一方、集客や運営コストの課題も存在します。
自社の状況や目標を照らし合わせ、ECモールとの併用も含めて最適なEC戦略を検討し、ブランド成長の新たな一歩を踏み出しましょう。
大切なのは、これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、自社のブランドの特性、事業規模、目標、そしてかけられるリソース(人材、時間、予算)を総合的に考慮して、自社ECサイトという選択肢が本当に適しているのかを慎重に判断することです。
ECモールへの出店を継続しながら、補完的な役割として自社ECサイトを運営するという「ECモールとの併用戦略」も有効な手段のひとつです。
それぞれのチャネルの強みを活かし、弱みを補い合うことで、より強固なEC事業を築くことができるでしょう。
しるし株式会社では、AmazonをはじめとしたECモールの運用代行サービスを提供しています。
ご相談は下記フォームから無料で受け付けていますので、まずは気軽にお問合せください。
⇒まずは無料相談する