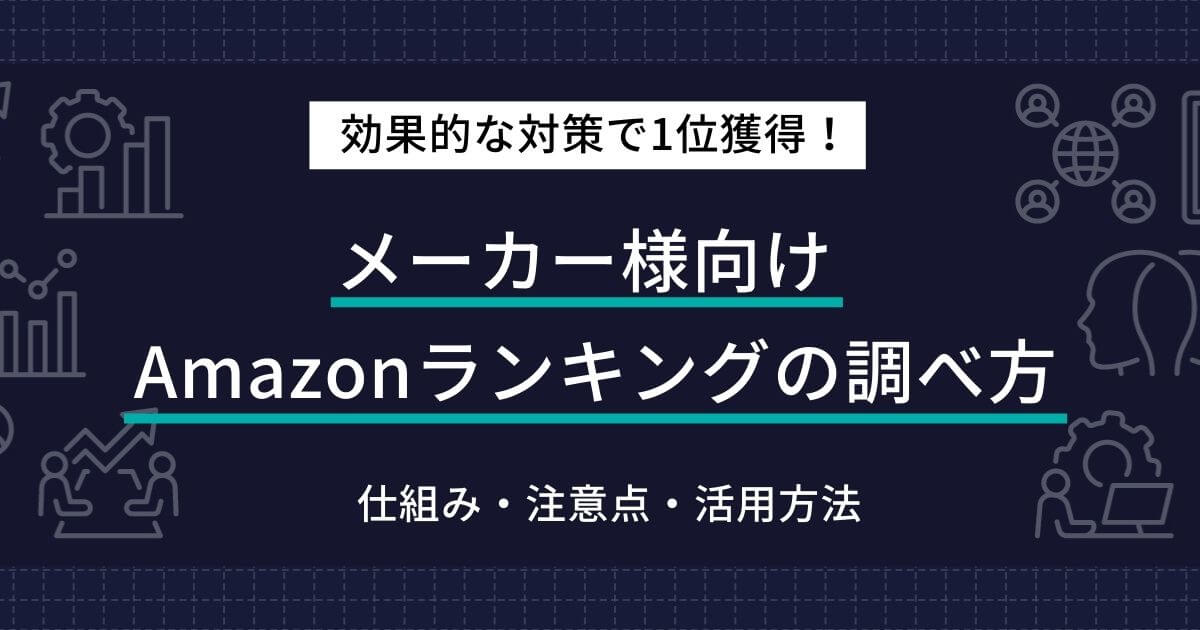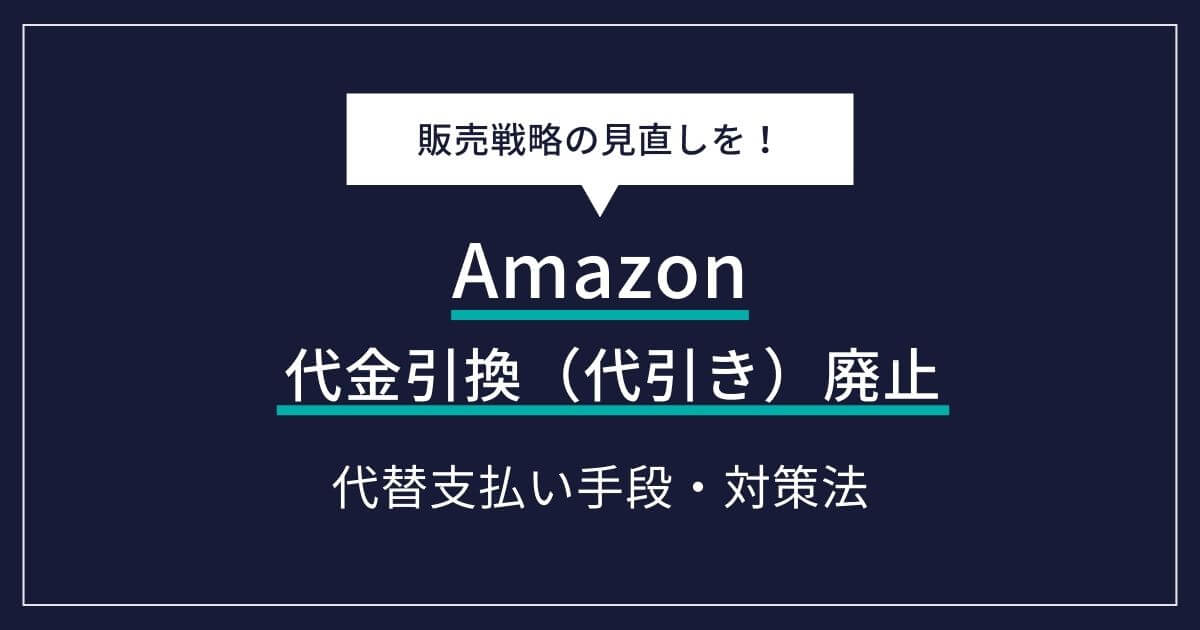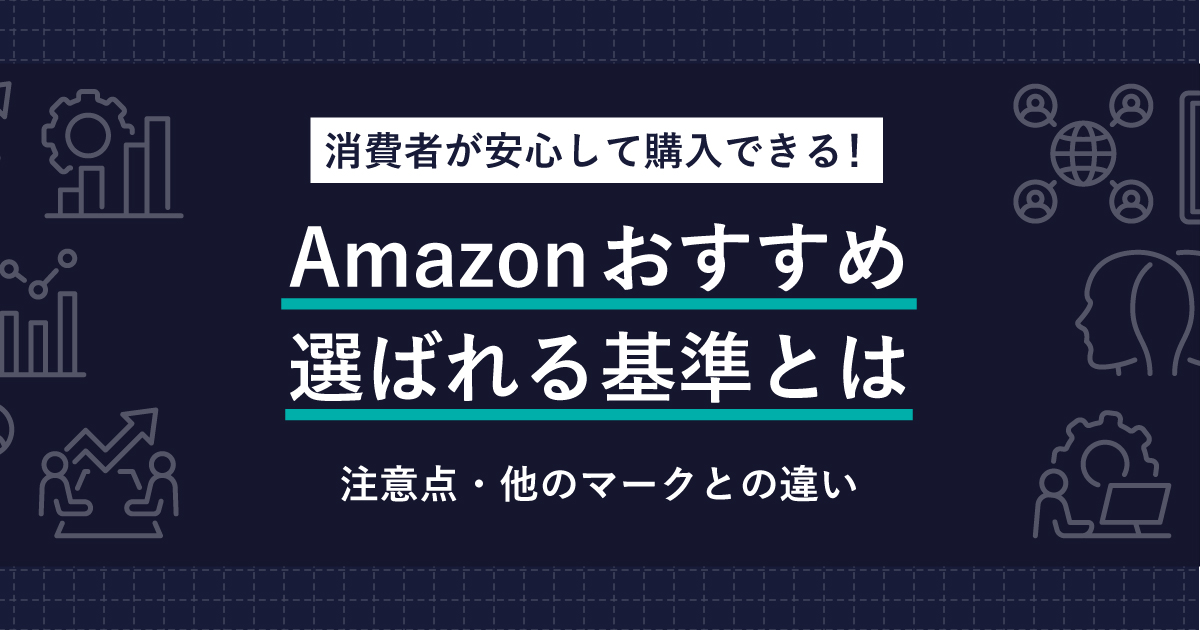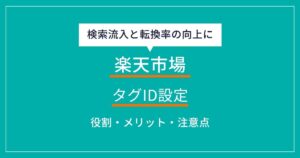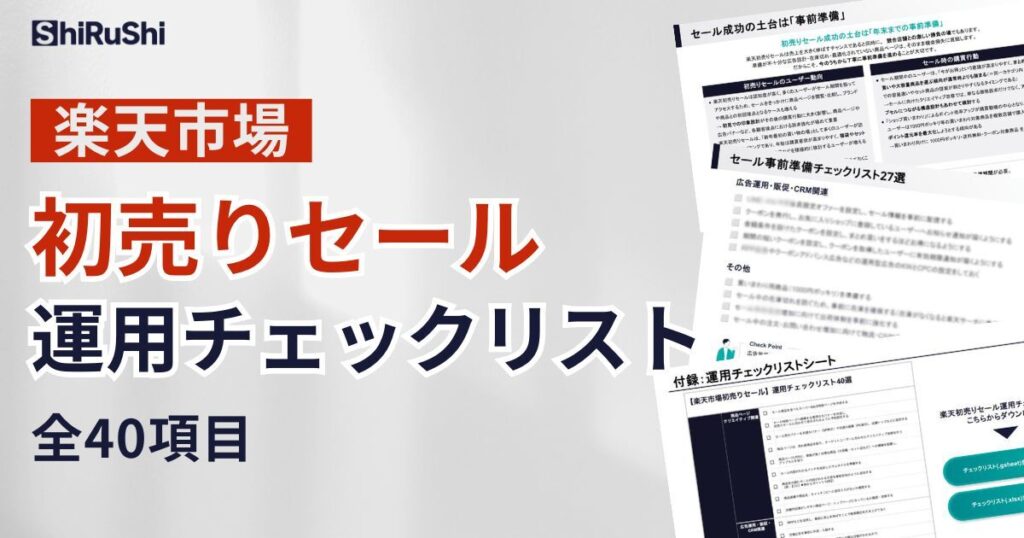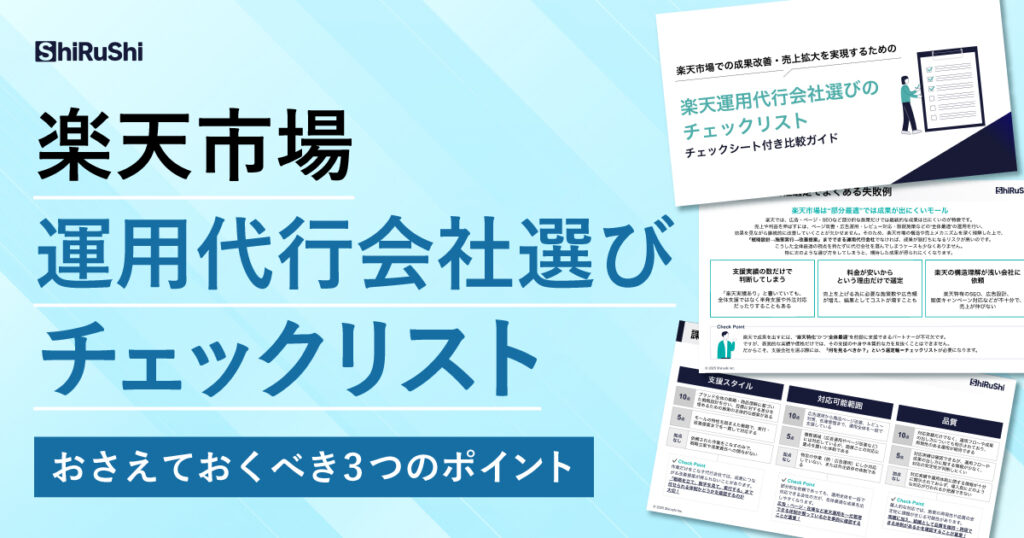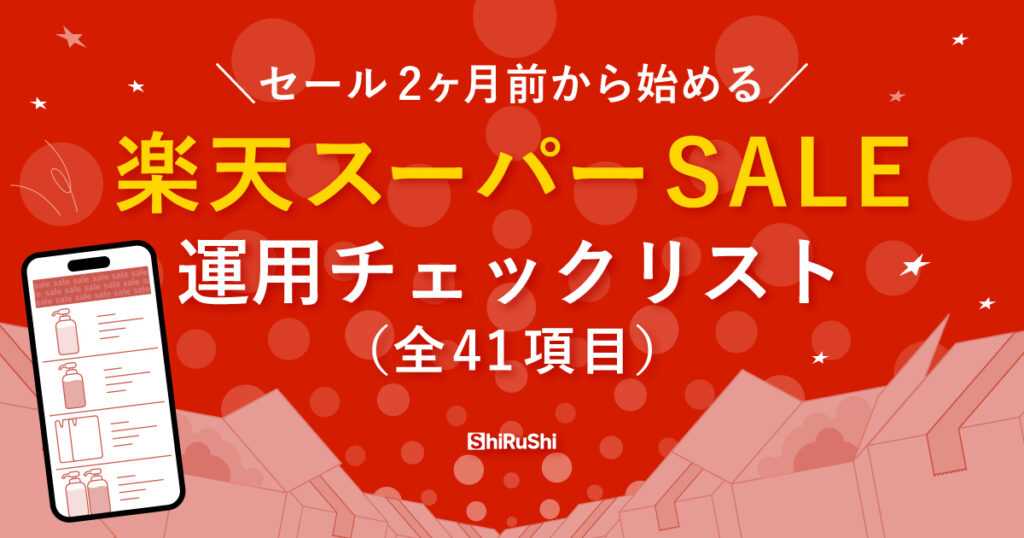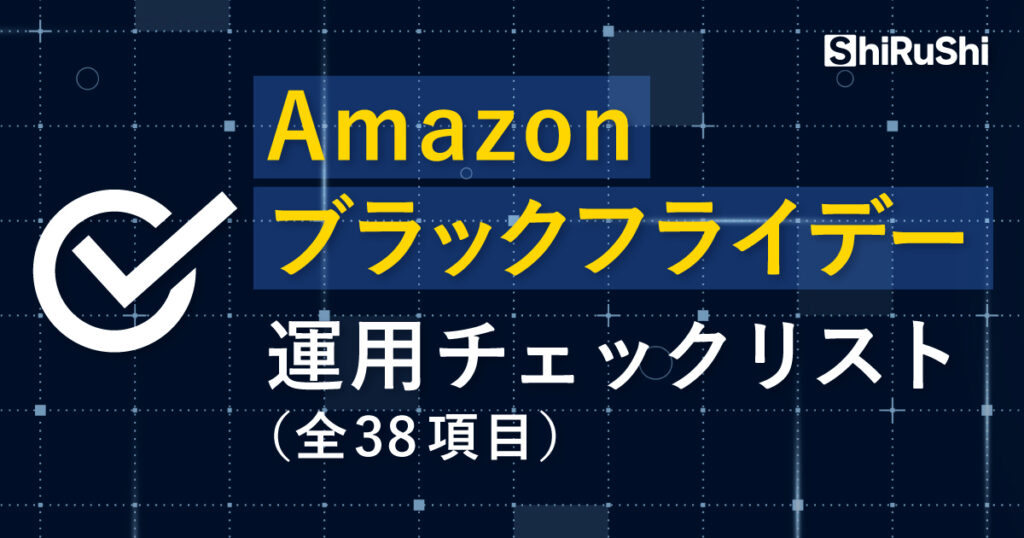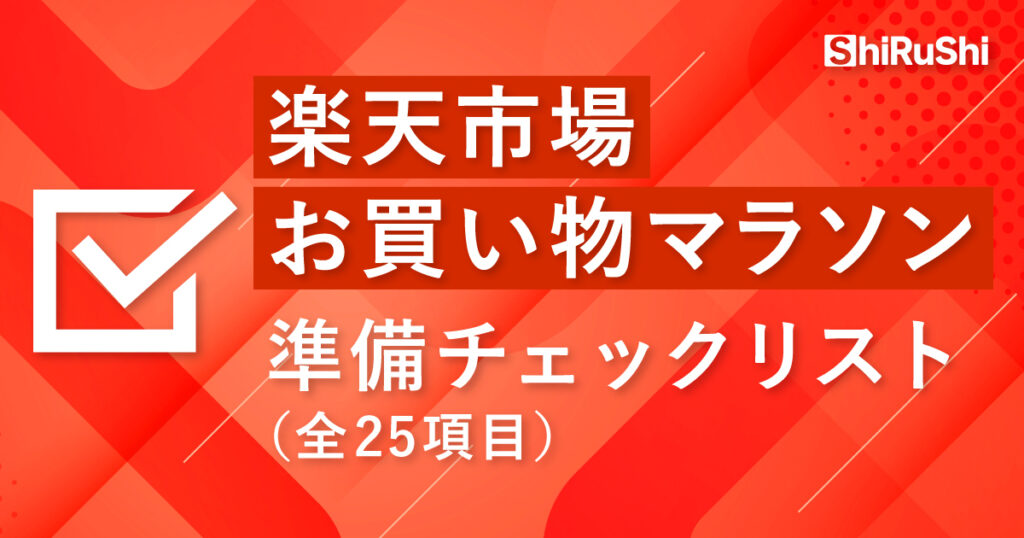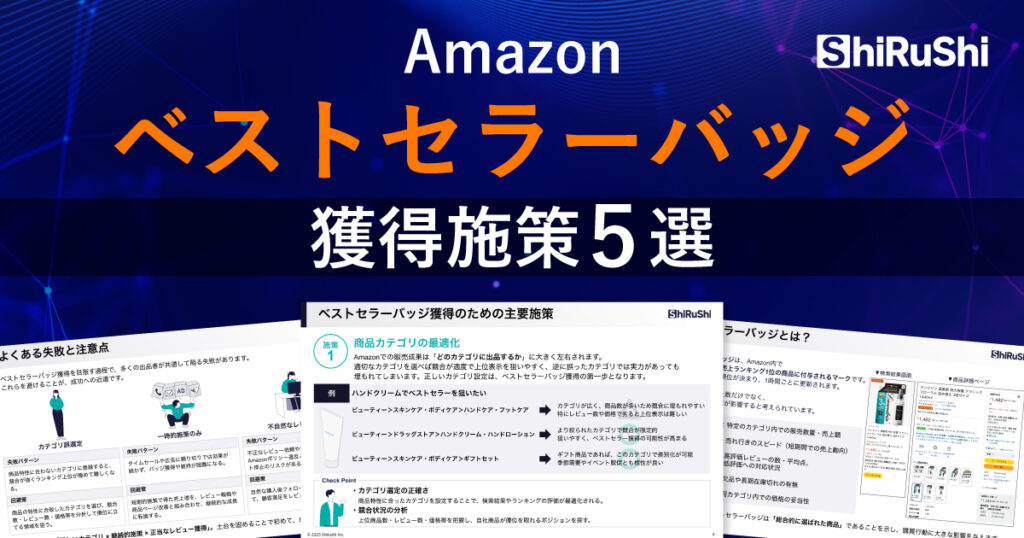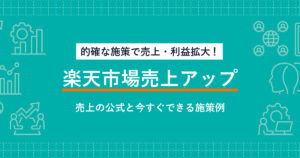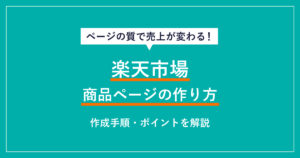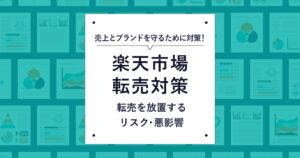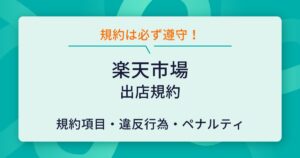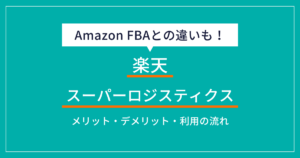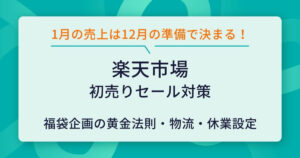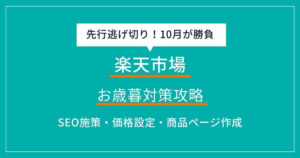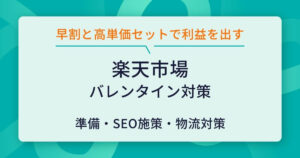Rakuten Analyticsとは?売上を伸ばすデータ分析の基本から店舗の課題別実践活用法まで徹底解説
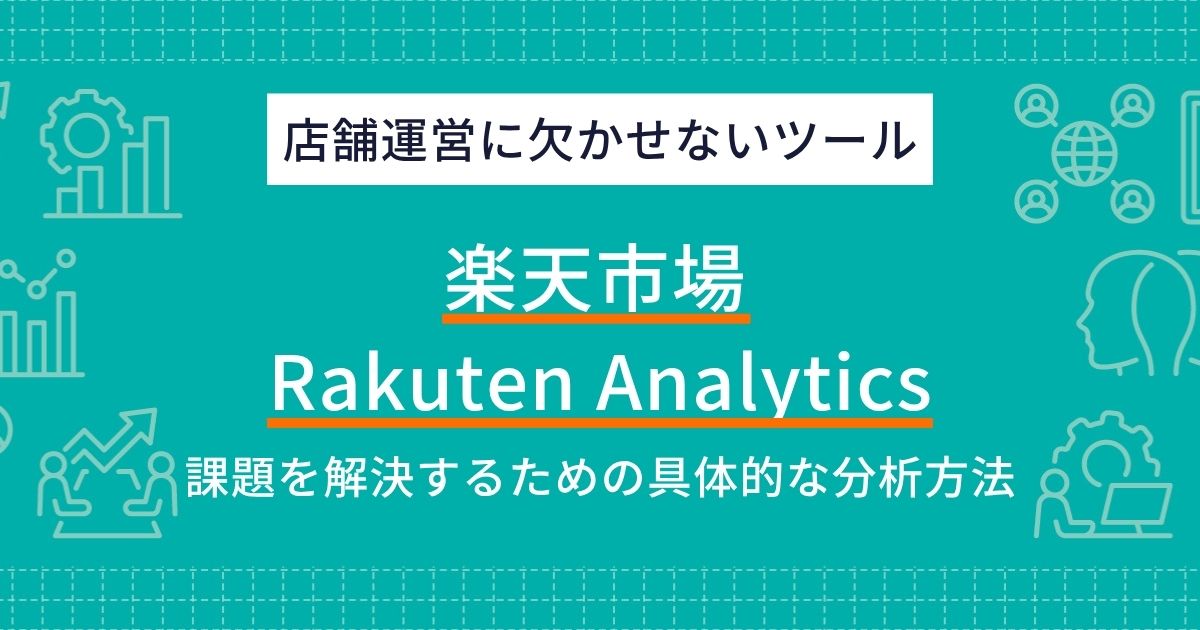

帯刀 浩太
楽天市場専任コンサルタント
楽天グループ株式会社にて、ECコンサルタントとして500社以上の店舗を支援。全ジャンルを幅広く担当した後、ホームライフ・リテール領域を中心に活躍し、年間売上改善部門MVPおよび楽天賞(社長賞)を受賞するなど、高い成果と評価を得る。その後、しるし株式会社にて、美容コスメ・ファッション・スポーツ分野の企業を中心に、楽天市場における戦略設計から店舗立ち上げ、LP制作、広告運用までを一気通貫で担当。楽天市場の構造や施策に精通し、実践的な支援を行う楽天運営のスペシャリスト。

監修者
帯刀 浩太
楽天市場専任コンサルタント
楽天グループ株式会社にて500社以上の店舗を支援。現在はしるし株式会社にて、戦略設計から店舗立ち上げ、広告運用までを一貫して担当。
「Rakuten Analytics」という言葉は知っているけれど、RMSの分析機能と何が違うのか、どう活用すれば売上アップに繋がるのか分からない…そんなお悩みはありませんか?
この記事では、楽天市場の店舗運営に欠かせないツール「Rakuten Analytics」の基本的な見方から、多くの店舗が抱える「アクセス改善」「転換率向上」「リピーター育成」といった課題を解決するための具体的な分析方法まで、徹底的に解説します。
Rakuten Analyticsとは?
Rakuten Analyticsは楽天グループのビッグデータを活用した最新の分析プラットフォームです。
楽天市場の標準分析機能(RMS内のR-カルテなど)とは一線を画し、マーケット全体の動向や顧客属性を幅広く分析できます。
ここでは、従来のRMSデータ分析機能との違いと、Rakuten Analyticsを利用すべき主な理由を解説します。
RMSの既存データ分析機能との決定的な違い
楽天市場の管理システムRMSにも店舗カルテ(R-カルテ)をはじめとした基本的なデータ分析機能があります。
しかし、Rakuten AnalyticsにはRMS標準機能にはない強みが多数存在します。以下の表に、RMSの分析とRakuten Analyticsの主な違いをまとめました。
| 比較項目 | RMSのデータ分析機能 (店舗カルテ等) | Rakuten Analytics |
|---|---|---|
| 分析データ範囲 | 自社店舗内のデータのみ(例:アクセス数・転換率など) | 楽天全体のビッグデータ(楽天IDに基づくオンライン・オフラインの行動まで網羅) |
| 分析できる内容 | 自社サイトの売上構成やページ訪問状況の把握が中心 | 市場トレンドや競合分析も可能。膨大なユーザーデータをもとに高精度な分析ができる |
| インターフェース | 固定フォーマットのレポートが中心 | 直感的なダッシュボードでカスタマイズ可能。グラフでデータを視覚化しやすい |
| 利用コスト | 標準機能として無料で利用可能 | 有料サービス(具体的な料金は非公開、要問い合わせ) |
RMSの店舗カルテでは自社サイト内の「アクセス人数」「転換率」「客単価」などの基本指標は確認できます。
しかしRakuten Analyticsでは、楽天全体のユーザー統計データを活用し、市場全体での自社の立ち位置や顧客像を分析可能です。
また、楽天が蓄積したデータはAIにより4,000以上の属性に分類されており、これを自社顧客情報と紐づけてより立体的な分析ができます。
こうした決定的な違いにより、Rakuten Analyticsは単なるアクセス解析を超えた経営判断ツールとなっています。

Rakuten Analyticsを使うべき理由
では、なぜ楽天出店企業がRakuten Analyticsを活用すべきなのでしょうか。主な理由は以下のとおりです。
- 楽天のビッグデータ活用
天エコシステム(経済圏)内の膨大なユーザーデータを活かし、従来見えなかった顧客の姿や市場ニーズを発見できます。例えば、市場動向や競合状況も含めた分析ができるため、戦略の精度が格段に上がります。
- 意思決定の高速化
直感的なダッシュボードでデータが可視化されるため、経営陣も素早く状況把握できます。データ量だけでなくスピード面でもメリットが大きいのがRakuten Analyticsの特徴です。
- 売上アップに直結
自社サイト内の改善点発見から、新規集客やリピーター育成まで、後述するように店舗運営の課題解決に直結する分析が可能です。データに基づき施策を打つことで無駄を減らし、効率よく売上向上を図れます。
このように、Rakuten Analyticsは楽天市場でのビジネス拡大を目指す企業にとって強力な武器となります。
「データに基づいた意思決定を行いたい」「競合に負けない戦略を立てたい」という場合に、導入を検討すべきでしょう。
高度な分析で「自社の立ち位置」や「課題」を可視化した後は、それを解決するための具体的なアクションが必要です。
分析結果を確実に数字へ繋げるために、今すぐ実践できる「売上アップ施策8選」をまとめた資料をご用意しました。下記よりダウンロードしてご活用ください。
⇒楽天市場売上アップ施策8選をダウンロードする
【店舗の課題別】売上アップに直結するRakuten Analytics実践活用術
ここからは、楽天店舗が直面しがちな課題ごとにRakuten Analyticsを使った解決策を紹介します。
アクセス数が伸びない、転換率(CVR)が低い、リピーターが増えない、広告効果を測りたいといった悩みに対し、Rakuten Analyticsで何を分析し、どう改善につなげるかを解説します。
データに基づくアプローチで、売上アップに直結する実践術を見ていきましょう。
課題1:アクセス数が伸び悩んでいる|流入経路分析で集客のボトルネックを発見する
「ページへのアクセス数(訪問者数)が思うように増えない」とお悩みの場合、まずは集客の現状を把握することが重要です。
Rakuten Analyticsの流入経路分析レポートを使えば、自社サイトへの流入経路の内訳が明らかになります。
例えば、流入分析の結果を見てみると「全アクセスのうち楽天市場内検索からが80%、楽天広告経由は数%、外部サイトからの流入はほぼゼロ」といったケースがあるかもしれません。
これはつまり、楽天内検索頼みで他の集客チャネルが弱い状態です。ボトルネックが判明すれば対策も立てやすくなります。
楽天内SEO対策で商品ページのキーワード最適化を図る、楽天広告やアフィリエイトを活用して楽天外から新規顧客を呼び込む、など弱点チャネルの強化につなげられるでしょう。
逆に、アクセス元の大半が特定の広告キャンペーンに偏っている場合は、広告停止時のリスクも浮き彫りになります。
こうした分析を通じて、集客面で注力すべきポイントを見極め、リソース配分の見直しや新たな集客策の導入を検討しましょう。
課題2:転換率が低い|顧客の回遊・離脱分析でカゴ落ちの根本原因を探る
サイトに来ているものの購入転換率(CVR)が低い場合、どこかに購買までの障壁があります。
Rakuten Analyticsでは、顧客のサイト内での回遊状況や離脱ポイントをデータで追跡できます。特に注目したいのが、各ページの直帰率やカート投入後の離脱率(カゴ落ち率)です。
商品ページの直帰率が高ければ「ページ内容に問題がある可能性」が考えられます。
例えば商品説明が不足している、画像が魅力的でない、価格が割高に感じられる、といった理由で商品ページから離脱されているかもしれません。
Rakuten Analyticsで該当ページの閲覧数と購入率を照らし合わせ、「閲覧はされているのに購入に至らない」商品があれば要注意です。
ページ改善(詳細情報の充実、レビューの掲載、価格見直し等)や、関連商品のレコメンド強化などの施策を検討しましょう。
また、カゴ落ち率の高さは「カートに商品は入れたがお会計まで進まなかったユーザー」が多いことを示します。
原因としては送料・手数料への不満や、決済ページまでの導線が分かりにくいなどが考えられます。
Rakuten Analyticsで特定期間のカート投入数と購入完了数を比較し、「カート投入のうち購入完了は○%」と把握できます。この数字が低ければ、カゴ落ち対策を強化しましょう。
具体策として、〇円以上購入で送料無料にする、期間限定のクーポンで後押しする、カート画面でのリマインドメールを工夫する(「あと少しで送料無料」など)と、いった施策が有効です。
データが示す離脱ポイントに的確に対処することで、転換率アップ=売上アップに直結します。
Rakuten Analyticsなら、感覚ではなく根拠をもってサイト改善に取り組めるため、無駄のないPDCAを回せるでしょう。
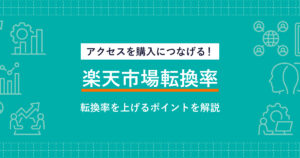
課題3:リピーターが増えない|顧客分析レポートで優良顧客を育成する施策を見つける
新規顧客は獲得できているものの、リピート購入に繋がらない…これも多くの店舗が直面する課題です。
楽天市場で売上を伸ばすには、新規客の獲得と同時にリピーターの育成が欠かせません。Rakuten Analyticsの顧客分析レポートを活用し、リピーター増加のヒントを探りましょう。
まず、レポートで新規とリピーターの購入比率や一人当たり購入回数を確認します。
リピーターの割合が低い場合は、獲得した新規客が定着していないことを意味します。原因を考えるには、リピーターになっている顧客層に注目します。
例えば顧客分析で、リピート購入している人の多くが「30代女性」で「子供向け商品を複数回購入」していると分かれば、その層に共通するニーズが見えてきます。
「30代子育て層」がリピートしやすい傾向があるなら、該当商品ラインナップの拡充や、関連商品のセット割引クーポン配布などが効果的かもしれません。
また、優良顧客(累計購入金額や頻度が高い顧客)の分析も重要です。
Rakuten Analyticsを使えば優良顧客の購買傾向や平均購入額が把握できるため、顧客の満足度をさらに高める施策を検討できます。
上位○%の顧客だけに限定セールの案内を出したり、誕生日クーポンを贈るといったVIP待遇で、ロイヤルティ向上を図ることができます。
「誰に対してどんな施策を打つべきか」をデータが教えてくれるので、感覚的な施策よりも効率よくリピーター育成につなげられるでしょう。
リピーターが増えれば安定した売上基盤が築けます。Rakuten Analyticsの顧客分析によって、自社サイトならではのリピート促進策を見出し、ぜひ実践してみてください。
課題4:広告やセールの効果を正しく知りたい|施策の効果測定とPDCAの回し方
楽天市場では、スーパーSALEやお買い物マラソン、クーポン発行、楽天広告の運用などさまざまな販促施策を行います。
「打った施策の効果をちゃんと測定し、次につなげたい」という場合にも、Rakuten Analyticsが役立ちます。
重要なのは、施策前後のデータを比較して検証することです。
Rakuten Analyticsなら、期間ごとのアクセス数・売上推移はもちろん、クーポン利用者の購買傾向や広告経由の転換率なども追跡できます。
例えば、楽天スーパーSALE期間中と通常時のアクセス数・売上高の増減を比較すれば、施策全体のインパクトが把握できます。
さらに、クーポンを発行した場合の使用率と、それが購買にどれだけ結び付いたか(クーポン利用者の転換率)を分析すれば、次回以降そのクーポン施策を継続すべきか見極められます。
スーパーSALE後にRakuten Analyticsでデータをチェックしてみましょう。
セール期間中の売上が通常時と比べてどのカテゴリで何%伸びたか、アクセスはどのチャネルから増えたか、逆に思ったほど効果が出なかった施策は何か、といったことが数字で示されます。
「○○カテゴリーの商品はセール中に売上2倍になったが、広告を出した△△商品の売上はあまり変わらなかった」など具体的な結果が見えれば、次回はより効果の高いカテゴリに注力し、効果の薄かった広告のクリエイティブを改善する、といったPDCAサイクルを回せます。
このようにデータに基づいて施策を振り返ることで、無駄なコストを省き効果的なマーケティング戦略を構築できます。
Rakuten Analyticsは施策の良し悪しを客観的に判断する「ものさし」となり、継続的な売上アップに欠かせない存在となるでしょう。
各課題に対し、「具体的に何をすればいいのか」という解決策を8つ厳選してホワイトペーパーにまとめました。 「分析結果ごとの打ち手がわからない」「PDCAをもっと早く回したい」という方は、ぜひダウンロードしてください。
⇒楽天市場売上アップ施策8選をダウンロードする
Rakuten Analyticsをより効果的に使うための注意点
非常に便利なRakuten Analyticsですが、正しく活用するために押さえておきたい注意点もあります。
- データが反映されるタイミングと計測期間の仕様
- 「アクセス人数」や「ユニークユーザー」など指標の定義を正しく理解する
これらを理解しておくことで、誤った解釈による判断ミスを防ぎ、より効果的にデータ活用ができるようになります。
データが反映されるタイミングと計測期間の仕様
Rakuten Analyticsのデータは、、リアルタイムに即反映されるわけではない点に注意しましょう。
一般的に、アクセス解析データには集計のタイムラグがあり、Rakuten Analyticsでも前日までの数値が翌日に反映される、といったケースがあります(※正確な反映サイクルは楽天の仕様によります)。
そのため、セール直後などすぐに分析したい場合でも、最新データの反映を待ってから正確に評価することが大切です。
また、計測期間の設定にも気を配りましょう。
デフォルトでは直近7日間や30日間といった期間でデータが表示されることがありますが、自分が分析したい期間にちゃんと切り替えているか確認が必要です。
期間の切り替えを誤ると、「先月は良かったのに今月急に数字が悪化した」と早合点してしまう恐れがあります。
セール効果を測定するなら、セール期間+前後期間を含めた分析期間を設定しないと正しい増減が掴めません。比較検証する際は同一条件で期間設定を行い、公平な比較を心がけましょう。
さらに、Rakuten Analyticsで扱うデータには実測値と予測値が混在している点も理解が必要です。
楽天独自のAI分析により推定されたユーザー属性データ(予測値)も提供されますが、これはあくまで統計的な推定です。
実際の登録情報など事実に基づくデータとAI推測データを区別し、それぞれの性質を踏まえて活用することが重要です。
「○○の可能性が高い」というデータは、絶対的な事実ではなく確率論的な示唆ですので、施策に落とし込む際には他の指標もあわせて検討しましょう。
「アクセス人数」や「ユニークユーザー」など指標の定義を正しく理解する
データ分析における指標の正しい定義を理解しておかなければ、分析結果を誤解してしまいます。
Rakuten AnalyticsやRMSで頻出する「アクセス人数」「ユニークユーザー(UU)」といった指標について整理しておきましょう。
- アクセス人数
アクセス人数は、ページ訪問から30分以内の訪問を1とカウント、30分以上経過して再訪問した場合には新たに1カウントされます。
- ユニークユーザー(UU)
指定した期間内で何人のユーザーがサイトに訪れたかを表す人数指標です。楽天市場では楽天会員IDなどで集計され、同じユーザーは期間内1人とカウントされます。
この違いを理解せずにいると、例えば転換率(CVR)の計算を見誤る恐れがあります。
実際に楽天市場では、以前は転換率(CVR)を「購入件数 ÷ UU」で算出していましたが、現在は「購入件数 ÷ アクセス人数」に公式変更されています。
分母をユニークユーザーからセッションに変えたことで数値は小さくなりますが、これは延べ来訪回数で割るほうが実態に即しているためです。
この変更を知らないと「集客は増えたのに転換率(CVR)が下がった?」と誤解してしまう店舗も出かねません。
Googleアナリティクス等に慣れている方でも、楽天独自の計測ルールや用語に戸惑う場合があります。
必ず楽天の公式ドキュメントやヘルプで定義を確認し、「何を意味する数字か」を正しく捉えましょう。
指標の意味を誤解しないことで、データが示す本当の状況を把握でき、的確な意思決定につながります。
Rakuten Analyticsを効率的に活用したいなら運用代行・コンサルの利用がおすすめ
Rakuten Analyticsは強力な分析ツールですが、使いこなすには時間と専門知識も要求されます。
日々のショップ運営に追われる中で、「データ分析まで手が回らない」という企業も多いでしょう。
そんなときは、楽天市場の運用代行やコンサルティングサービスを活用するのもおすすめです。
実際に、楽天市場出店企業の中には「社内にノウハウがない」「担当者が退職してリソースが不足している」といった悩みを抱えているケースも少なくありません。
楽天市場の運用代行・コンサルティングを行っているしるし株式会社では、無料相談を受け付けています。
プロの視点でRakuten Analyticsの分析結果を読み解き、売上アップのための具体的な施策提案が可能です。
自社では気が付けないデータの示唆や、豊富な成功パターンに基づく改善策を得られるのは、専門家に任せる大きなメリットでしょう。
また、日々の運用実務を外部に任せることで、社内リソースを「商品開発」や「販促企画」といった本来注力すべき業務に集中させることができます。それぞれの得意分野を活かすことで、事業全体の成長スピードを加速させることが可能です。
「データは取ったものの活かしきれていない」「もっと効率よく楽天市場で成果を出したい」という場合は、プロの力を借りることも検討してみてください。
無料相談を賢く活用することで、自社に最適なデータ活用法や運用戦略のヒントをもらえるはずです。
⇒しるしに無料相談する
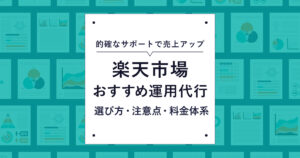
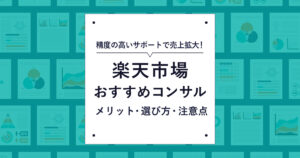
Rakuten Analyticsを使いこなしデータに基づいた店舗運営を実現しよう
楽天市場の新しいデータ分析ツールであるRakuten Analyticsは、売上やアクセス数といった基本指標から、顧客行動や市場動向までを可視化できる優れた機能を備えています。
これを上手に使いこなせば、経験や勘に頼っていた従来の運営から一歩抜け出し、データに裏付けられた戦略的な店舗運営が可能になります。
もちろん、ツールを導入するだけで成果が出るわけではありません。大切なのは分析結果に基づいて迅速に施策を実行し、効果検証して改善を続けること(PDCA)です。
データ活用に不安がある方は、遠慮なく専門家に頼るのもひとつの方法です。しるし株式会社では無料相談を随時受け付けていますので、必要に応じて活用してみてください。
Rakuten Analyticsを使いこなし、データに基づいた意思決定で楽天市場のビジネスを飛躍させましょう。
⇒しるしに無料相談する
楽天市場の運用代行・コンサルティングなら「しるし株式会社」へ!

| 運営会社 | しるし株式会社 |
|---|---|
| 料金タイプ | 完全成果報酬 |
| 対応領域 | ・楽天市場 ・Amazon ・Qoo10 ・Yahoo!ショッピング |
| サポート内容 | ・戦略施策立案 ・TOPページ・商品ページ制作、最適化 ・楽天 SEO対策 ・広告運用 ・データ分析 ・効果測定 ・CRM施策(メルマガ運用) ・楽天市場社員との窓口など |
| 公式HP | https://shirushi.co.jp/ |
しるし株式会社は、ブランドのグロースパートナーとして、ECモールにおける売上目標設定、戦略立案、実行まで、一気通貫したサービスを提供しており、楽天との連携に特化したLINE運用ツールも開発中。
ひとりのコンサルタントが運用するのではなく、戦略担当やクリエイティブ担当など各領域のプロで結成したチームで運用をサポートしています。
SEOや広告運用、商品ページ改善、レビュー管理、アップセル・クロスセル施策、セール対応など、モールの課題に応じた戦略・施策の実行で売上拡大を実現しているのが強みです。
数あるEC運用の代行会社のなかで、なぜしるし株式会社がお選びいただけているのか。しるしの強みを3つ紹介します。
しるしの強み① ブランド基点のモール運用
しるしは、ECモール運営においてブランド価値の向上を中核に据えた独自のアプローチを展開しています。
一般的なECモール運用が値引きや販促活動に主眼を置く中、しるしのメソッドはブランドのアイデンティティを基軸とした商品ページ構成、魅力的なブランドストーリーの構築、顧客体験の徹底的な改善に注力します。
この戦略により、即時的な売上増加のみならず、長期的なブランドロイヤリティの形成と顧客生涯価値の増大を目指しています。
ECモール内での一貫したブランド体験を実現することで、競争激化するオンライン市場において差別化された存在感の確立が可能です。
しるしの強み② 売上・粗利にコミットする料金形態
しるしは売上にコミットした運用を行うため、料金形態も売上連動型を採用。作業や時間ではなく、成果に連動して料金が決まります。
メーカーさま同じ方向を向いて事業を伸ばすには、ベストな契約形態だと考えています。
しるしの強み③ スペシャリストにEC運用をまるっとおまかせで工数削減!
「EC運用をどのくらいできていますか?」と聞かれると、自信を持って答えられない……という担当者さまも多いです。
売上を上げるには、市場、ECモール、商材に合わせた戦略立案が重要。特にECモールにはそれぞれ特色や独自の制度があるため、施策の最適化には骨が折れます。ものづくりをしている会社が、EC運用業務を内製するのは、時間も労力もかかりすぎると感じませんか?
しるしの運用では、各パートのスペシャリストがチームを組み、貴社の商品のポテンシャルが最大限発揮されるよう運用します。1ブランドに対して、アカウント担当や商品ページ担当、デザイナーなどの楽天市場グロースチームを結成し、専門性の高いチームで商品・ブランドがもつポテンシャルを最大限に引き出せるのが強みです。
しるしの強み④ 管理画面では見れない情報が見れる、分析ダッシュボードの作成
楽天市場のRMSでは見ることのできない指標まで分析可能なダッシュボードを作成し、運用を行います。
例えば、「LTVの計測ができない」「次回購入までにかかる期間がわからない」「選択肢ごとの売上の管理ができない」といったRMSにありがちな課題を解消し、運用や目標管理を行います。
また、毎月のレポートはPL形式で行います。売上が上がっているかだけではなく、販促費や物流費の最適化も管理。売上・粗利率の最大化を目指します。
⇒まずは無料相談する
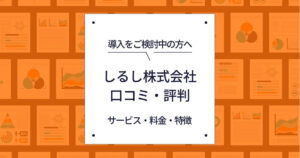

帯刀 浩太
楽天市場専任コンサルタント
楽天グループ株式会社にて、ECコンサルタントとして500社以上の店舗を支援。全ジャンルを幅広く担当した後、ホームライフ・リテール領域を中心に活躍し、年間売上改善部門MVPおよび楽天賞(社長賞)を受賞するなど、高い成果と評価を得る。その後、しるし株式会社にて、美容コスメ・ファッション・スポーツ分野の企業を中心に、楽天市場における戦略設計から店舗立ち上げ、LP制作、広告運用までを一気通貫で担当。楽天市場の構造や施策に精通し、実践的な支援を行う楽天運営のスペシャリスト。

監修者
帯刀 浩太
楽天市場専任コンサルタント
楽天グループ株式会社にて500社以上の店舗を支援。現在はしるし株式会社にて、戦略設計から店舗立ち上げ、広告運用までを一貫して担当。